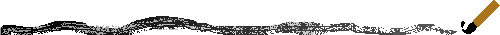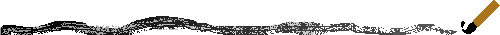『 ぼくの家族
5年2組 中在家 作兵衛
ぼくのうちは、父と弟の平太としんべヱと
喜三太とぼくの、5人家族です。母は、喜三
太が生まれてすぐに、病気で死にました。
喜三太はこの間1才になったばかりで、し
んべヱはもうじき3才で、平太はもうじき5
才です。3人とも、ぼくの大事な弟です。父
は、やさしくてまじめでかっこいい人です。
でも、ぼくと父は本当の親子ではないから、
いらない子なんだと、母のおそうしきの時に
しらないおじさんに言われました。
(後略)』
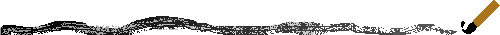 息子の担任教師に「お話が…」と呼び出され、上記の作文に目を通した
留三郎は、目の前の担任教師以上に困惑した顔をしていた。
「あ、あの。その、ここに書かれていることは…」
作文を持ったまま固まった留三郎に、どう言葉をかけていいかわからない
担任教師がオロオロと目を泳がせながら、それでもどうにか問い掛けると、
留三郎は苦笑交じりに「おおむね事実です」と呟いた。
「作兵衛は、亡くなった妻の連れ子でして。…しかし、下の子達と
同様に扱ってきたつもりですし、大切な息子だと思っています」
作兵衛の実父は作兵衛が1歳の頃に事故死しており、母親と留三郎が
再婚したのは作兵衛は4歳になる少し前のことだったため、おぼろげに
しか覚えていないようだ。と留三郎は判断し、あえて教えて波風を立てる
こともないだろうと言わないでいた。
確かに妻が死んで以降、作兵衛がどこか自分に対してよそよそしい態度を
とったり、遠慮しているように感じることはあった。けれどそれは、思春期
だからなのだろうと、留三郎は思っていた。
故に留三郎は、誰だかは判らないが、心無い言葉で事実を歪めて作兵衛に
吹き込んだ相手を恨み、同時にそれを鵜呑みにされてしまう程度のことしか
出来ていなかったらしい自分を不甲斐なく感じた。
「ご迷惑とご心配をおかけしました。帰ったら本人とも話してみますので、
この作文はお借りしてもよろしいでしょうか?」
そう断わって小学校を辞した後。留三郎はそのまま帰宅はせずに、
伯父の家に向かった。しかし目的は伯父の新野洋一ではなく、
そこに居候している妹の伊作だった。
彼女は―理由はイマイチ解らないが―現在家出中の身ではあるが、
14歳から5歳までの7児の母であり、職業は保育士で、かつ留三郎の
所の4人を含む甥姪の面倒もよく看てくれている。そのため、
相談相手として最も適切だと考えたのだった。
「…ごめん」
作文に目を通すなり、伊作は謝罪を口にしてきた。
留三郎はそれを
「自分では力になれそうも無い」
という意味に採りかけたが、伊作は続けて
「この、”知らないおじさん”って、多分ウチのお義父さん…」
と、申し訳なさそうに呟いた。
伊作の夫である潮江文次郎と、その実父の夏之丞の仲は険悪である。
しかし、夏之丞と留三郎の妻の父―吉野―が古い知人だったこともあり、
葬儀に呼ばざるを得なかった記憶はある。
そして彼なら、あのような発言をしかねないような気が、留三郎にもした。
「本っ当にごめん。アノ人が作ちゃんに話しかけてるのは、見かけた気が
するんだけど、『珍しいなぁ』って思っただけで放っといちゃって…」
「いや、いい。お前は悪くない。あの時は忙しかったんだから、仕方ない」
喪主の留三郎に代わり、食事の用意やらや弔問客の対応などに奔走していたのは、
主に妹の伊作と仙蔵と弟―小平太―の妻である滝夜叉丸で、珍しく子供達を夫達に
預けっぱなしで動き回っていた。そんな状況で「気付け」という方が難しい。
「…うん。でも、おわびに作ちゃんの説得はまかせて」
「ああ。頼んだ。…俺も、頑張ってはみるけどな」
うなだれていた顔を上げて、力強く言い切った伊作に、留三郎は少し励まされた。
息子の担任教師に「お話が…」と呼び出され、上記の作文に目を通した
留三郎は、目の前の担任教師以上に困惑した顔をしていた。
「あ、あの。その、ここに書かれていることは…」
作文を持ったまま固まった留三郎に、どう言葉をかけていいかわからない
担任教師がオロオロと目を泳がせながら、それでもどうにか問い掛けると、
留三郎は苦笑交じりに「おおむね事実です」と呟いた。
「作兵衛は、亡くなった妻の連れ子でして。…しかし、下の子達と
同様に扱ってきたつもりですし、大切な息子だと思っています」
作兵衛の実父は作兵衛が1歳の頃に事故死しており、母親と留三郎が
再婚したのは作兵衛は4歳になる少し前のことだったため、おぼろげに
しか覚えていないようだ。と留三郎は判断し、あえて教えて波風を立てる
こともないだろうと言わないでいた。
確かに妻が死んで以降、作兵衛がどこか自分に対してよそよそしい態度を
とったり、遠慮しているように感じることはあった。けれどそれは、思春期
だからなのだろうと、留三郎は思っていた。
故に留三郎は、誰だかは判らないが、心無い言葉で事実を歪めて作兵衛に
吹き込んだ相手を恨み、同時にそれを鵜呑みにされてしまう程度のことしか
出来ていなかったらしい自分を不甲斐なく感じた。
「ご迷惑とご心配をおかけしました。帰ったら本人とも話してみますので、
この作文はお借りしてもよろしいでしょうか?」
そう断わって小学校を辞した後。留三郎はそのまま帰宅はせずに、
伯父の家に向かった。しかし目的は伯父の新野洋一ではなく、
そこに居候している妹の伊作だった。
彼女は―理由はイマイチ解らないが―現在家出中の身ではあるが、
14歳から5歳までの7児の母であり、職業は保育士で、かつ留三郎の
所の4人を含む甥姪の面倒もよく看てくれている。そのため、
相談相手として最も適切だと考えたのだった。
「…ごめん」
作文に目を通すなり、伊作は謝罪を口にしてきた。
留三郎はそれを
「自分では力になれそうも無い」
という意味に採りかけたが、伊作は続けて
「この、”知らないおじさん”って、多分ウチのお義父さん…」
と、申し訳なさそうに呟いた。
伊作の夫である潮江文次郎と、その実父の夏之丞の仲は険悪である。
しかし、夏之丞と留三郎の妻の父―吉野―が古い知人だったこともあり、
葬儀に呼ばざるを得なかった記憶はある。
そして彼なら、あのような発言をしかねないような気が、留三郎にもした。
「本っ当にごめん。アノ人が作ちゃんに話しかけてるのは、見かけた気が
するんだけど、『珍しいなぁ』って思っただけで放っといちゃって…」
「いや、いい。お前は悪くない。あの時は忙しかったんだから、仕方ない」
喪主の留三郎に代わり、食事の用意やらや弔問客の対応などに奔走していたのは、
主に妹の伊作と仙蔵と弟―小平太―の妻である滝夜叉丸で、珍しく子供達を夫達に
預けっぱなしで動き回っていた。そんな状況で「気付け」という方が難しい。
「…うん。でも、おわびに作ちゃんの説得はまかせて」
「ああ。頼んだ。…俺も、頑張ってはみるけどな」
うなだれていた顔を上げて、力強く言い切った伊作に、留三郎は少し励まされた。
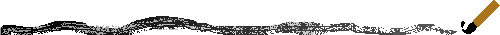 「作ちゃん久しぶり。元気なのはさもくん達から聞いてるよ」
(…相変わらず、この人は変だ)
問題の作文を提出した数日後。帰宅した所を笑顔で迎えてくれた叔母伊作に
対して、作兵衛がまず最初に思ったのはそんなことだった。
お決まりの「元気にしていた?」の代わりに「元気だと聞いている」は、まあ、
そこまでおかしくはない。しかし、その情報源である作兵衛と同じ小学校に通う
次男の左門は、伊作の家出の際に父親の元に残った筈である。
ということは、家出状態でも定期的に会うか連絡をとっているということだろう。
そもそもの家出理由からして、「何か文次郎に対して怒っているらしい」としか、
作兵衛は聞いていない。それ以上は、留三郎も解らないらしいし、左門にいたっては
訊くだけ無駄な気がする。「単純馬鹿」と「読めない人」の、似ていない母子だと
作兵衛は彼らを捉えている。
「…お久しぶりです。何の御用ですか?」
「作ちゃんとお話をしに。…留兄がね、作文のことで凹んでるんだ」
作兵衛は、留三郎が作文のことで呼び出されたのには、何となく気付いていた。
けれど何も言わず、普段通りに接してくる以上、自分からは切り出せなかった。
本心では、否定して欲しかったのだと思う。
たとえ血が繋がっていないことが事実だとしても、自分は疎まれていないと、
留三郎の口から聞きたくて、しかし面と向かって訊くのは怖くて、その内に
どんどん疑心暗鬼に駆られていき、以前のように無邪気には振舞えなくなった。
そして行き着いたのがあの作文であり、アレは一種の賭けだったのだ。
「結論から言っちゃうとね、たとえ実の親子でなくても、留兄は作ちゃんのこと
大好きだよ。…そりゃあもう、ウチの阿呆に見習わせたいくらいの溺愛っぷり」
伊作が知る中で、一番子供に甘いのは留三郎である。しかし、ただ無条件に
甘やかすのではなく、叱る時はキチンと叱るし、礼儀作法にも結構うるさい。
そういったアメとムチの使い分けが、一番巧いのも留三郎だと思っている。
「わかっては、いるんですけど…」
作兵衛だって留三郎の優しさを、疑いたくて疑っているわけではない。
けれど、「いつか見捨てられたらどうしよう」という思いが、葬儀の
日から頭から離れないのだ。
「ねえ、作ちゃん。『本当の親子かどうか』って、そんなに大事なことかな?」
7人も産んだ自分では、あまり説得力の無い言葉だと、伊作は解っている。
けれど、知り合いには血縁は無いがとても仲の良い義理の親兄弟もいるし、逆に
とんでもなく仲の悪い実の親子も知っている。というか、その「険悪な親子」が、
今回の騒動の原因なのだが。
「…お母さんのお葬式の時に、作ちゃんに酷いこと言った人が、多分文次の
お父さんだと思う。って言ったら、作ちゃんは信じる?」
「え? 叔父さんの、ですか?」
留三郎や仙蔵と仲が悪く、実の子供達にすらあまり懐かれていなかったりするし、
作兵衛の中では、何となく「怖い人」のイメージがある文次郎だが、それでも
アノ葬儀の嫌みったらしい男とは、似ても似つかない。作兵衛はそう思った。
「そう。文次の実の父親で、さもくん達にとってはもう一人のお祖父さん。だけど、
文次は毛嫌いしてるし、僕らも苦手なんで、あんまり関わらないでいるんだ」
基本的に人当たりの良い伊作に、ここまで苦手意識を持たれるとは、どれだけ
嫌な人間なのか。と、作兵衛は思ったが伊作は苦笑交じりに
「身内でなければ、ただの『ダジャレ好きのウザい脂オヤジ』ってだけで済むん
だろうけど、四六時中ダジャレを聞かされたり、ねちねち嫌味を言われるのは
キツくってねぇ。さっちゃんが生まれたくらいから、ほぼ絶縁状態なんだ」
と付け加えた。ちなみに、「さっちゃん」とは、長女の左近を指す。
「文次にはお姉さんがいるんだけど、そのお姉さんもお父さんのことが嫌いで、
さっさと家を出ちゃったんだ。とまあそんな感じで、自分が実の子供達に背を
向けられたもんだから、よそもそんな風だと思ってるみたいで、それが連れ子
だったらより一層。…って考えみたいなんだ」
だからって、お母さんを亡くしたばかりの小学生に、あんな酷いことを言って
いい訳が無いんだけどね。と、伊作は締めくくった。
「…つまり、ぼくと父さんが実の親子じゃないこと以外は、全部、勘違い?」
「そういうことだね。…それにしても、アレだけベタ甘な留兄と、『お兄ちゃん
大好きv』を全面に表してる弟くん達に囲まれてて、疑う気持ちの方が解んないや」
留三郎本人の口から聞いたわけでは無いので、まだ半信半疑の作兵衛に、伊作が
呆れたように呟くと、作兵衛は目を丸くして
「え? そんなに、ですか?」
と返してきた。…どうも、日常と化し過ぎていて自覚がなかったらしい。
「うん。実は留兄ってば、君達のお母さんにプロポーズを受けてもらえた時よりも、
初めて君に『お父さん』って呼んでもらえた時の方が、何倍も嬉しそうだった。とか、
結婚記念日は残業が入っちゃったのに、君達の誕生日の時には死に物狂いで仕事を
片付けてきた。とか、他にもことあるごとにお義姉さんよりも君達を優先しまくって
たから、『留さんは、あたしよりも作たちの方が大事なんだわ』っていうグチが、
口癖と化してたんだよ。実は」
愛妻家で子煩悩な留三郎は、若干子煩悩の方が勝っていたが、そんな痴話げんかや
グチですら微笑ましい、仲睦まじい夫婦であり、愛にあふれる一家なのだ。
そう言って、伊作は笑った。
その後。思春期的な意味で、ベタ甘な家族が少し恥ずかしくなった作兵衛に、
軽く距離を置かれて凹んだ留三郎が相談した時は、流石に伊作も
「それは、放っておくのが一番だと思うなぁ」
と答えたという。
「作ちゃん久しぶり。元気なのはさもくん達から聞いてるよ」
(…相変わらず、この人は変だ)
問題の作文を提出した数日後。帰宅した所を笑顔で迎えてくれた叔母伊作に
対して、作兵衛がまず最初に思ったのはそんなことだった。
お決まりの「元気にしていた?」の代わりに「元気だと聞いている」は、まあ、
そこまでおかしくはない。しかし、その情報源である作兵衛と同じ小学校に通う
次男の左門は、伊作の家出の際に父親の元に残った筈である。
ということは、家出状態でも定期的に会うか連絡をとっているということだろう。
そもそもの家出理由からして、「何か文次郎に対して怒っているらしい」としか、
作兵衛は聞いていない。それ以上は、留三郎も解らないらしいし、左門にいたっては
訊くだけ無駄な気がする。「単純馬鹿」と「読めない人」の、似ていない母子だと
作兵衛は彼らを捉えている。
「…お久しぶりです。何の御用ですか?」
「作ちゃんとお話をしに。…留兄がね、作文のことで凹んでるんだ」
作兵衛は、留三郎が作文のことで呼び出されたのには、何となく気付いていた。
けれど何も言わず、普段通りに接してくる以上、自分からは切り出せなかった。
本心では、否定して欲しかったのだと思う。
たとえ血が繋がっていないことが事実だとしても、自分は疎まれていないと、
留三郎の口から聞きたくて、しかし面と向かって訊くのは怖くて、その内に
どんどん疑心暗鬼に駆られていき、以前のように無邪気には振舞えなくなった。
そして行き着いたのがあの作文であり、アレは一種の賭けだったのだ。
「結論から言っちゃうとね、たとえ実の親子でなくても、留兄は作ちゃんのこと
大好きだよ。…そりゃあもう、ウチの阿呆に見習わせたいくらいの溺愛っぷり」
伊作が知る中で、一番子供に甘いのは留三郎である。しかし、ただ無条件に
甘やかすのではなく、叱る時はキチンと叱るし、礼儀作法にも結構うるさい。
そういったアメとムチの使い分けが、一番巧いのも留三郎だと思っている。
「わかっては、いるんですけど…」
作兵衛だって留三郎の優しさを、疑いたくて疑っているわけではない。
けれど、「いつか見捨てられたらどうしよう」という思いが、葬儀の
日から頭から離れないのだ。
「ねえ、作ちゃん。『本当の親子かどうか』って、そんなに大事なことかな?」
7人も産んだ自分では、あまり説得力の無い言葉だと、伊作は解っている。
けれど、知り合いには血縁は無いがとても仲の良い義理の親兄弟もいるし、逆に
とんでもなく仲の悪い実の親子も知っている。というか、その「険悪な親子」が、
今回の騒動の原因なのだが。
「…お母さんのお葬式の時に、作ちゃんに酷いこと言った人が、多分文次の
お父さんだと思う。って言ったら、作ちゃんは信じる?」
「え? 叔父さんの、ですか?」
留三郎や仙蔵と仲が悪く、実の子供達にすらあまり懐かれていなかったりするし、
作兵衛の中では、何となく「怖い人」のイメージがある文次郎だが、それでも
アノ葬儀の嫌みったらしい男とは、似ても似つかない。作兵衛はそう思った。
「そう。文次の実の父親で、さもくん達にとってはもう一人のお祖父さん。だけど、
文次は毛嫌いしてるし、僕らも苦手なんで、あんまり関わらないでいるんだ」
基本的に人当たりの良い伊作に、ここまで苦手意識を持たれるとは、どれだけ
嫌な人間なのか。と、作兵衛は思ったが伊作は苦笑交じりに
「身内でなければ、ただの『ダジャレ好きのウザい脂オヤジ』ってだけで済むん
だろうけど、四六時中ダジャレを聞かされたり、ねちねち嫌味を言われるのは
キツくってねぇ。さっちゃんが生まれたくらいから、ほぼ絶縁状態なんだ」
と付け加えた。ちなみに、「さっちゃん」とは、長女の左近を指す。
「文次にはお姉さんがいるんだけど、そのお姉さんもお父さんのことが嫌いで、
さっさと家を出ちゃったんだ。とまあそんな感じで、自分が実の子供達に背を
向けられたもんだから、よそもそんな風だと思ってるみたいで、それが連れ子
だったらより一層。…って考えみたいなんだ」
だからって、お母さんを亡くしたばかりの小学生に、あんな酷いことを言って
いい訳が無いんだけどね。と、伊作は締めくくった。
「…つまり、ぼくと父さんが実の親子じゃないこと以外は、全部、勘違い?」
「そういうことだね。…それにしても、アレだけベタ甘な留兄と、『お兄ちゃん
大好きv』を全面に表してる弟くん達に囲まれてて、疑う気持ちの方が解んないや」
留三郎本人の口から聞いたわけでは無いので、まだ半信半疑の作兵衛に、伊作が
呆れたように呟くと、作兵衛は目を丸くして
「え? そんなに、ですか?」
と返してきた。…どうも、日常と化し過ぎていて自覚がなかったらしい。
「うん。実は留兄ってば、君達のお母さんにプロポーズを受けてもらえた時よりも、
初めて君に『お父さん』って呼んでもらえた時の方が、何倍も嬉しそうだった。とか、
結婚記念日は残業が入っちゃったのに、君達の誕生日の時には死に物狂いで仕事を
片付けてきた。とか、他にもことあるごとにお義姉さんよりも君達を優先しまくって
たから、『留さんは、あたしよりも作たちの方が大事なんだわ』っていうグチが、
口癖と化してたんだよ。実は」
愛妻家で子煩悩な留三郎は、若干子煩悩の方が勝っていたが、そんな痴話げんかや
グチですら微笑ましい、仲睦まじい夫婦であり、愛にあふれる一家なのだ。
そう言って、伊作は笑った。
その後。思春期的な意味で、ベタ甘な家族が少し恥ずかしくなった作兵衛に、
軽く距離を置かれて凹んだ留三郎が相談した時は、流石に伊作も
「それは、放っておくのが一番だと思うなぁ」
と答えたという。
…前にしろちゃんの夏休みの日記を書いたときにも思ったんですが、
小学生の語彙がよくわかりません。(原作と近い年だけど何か違うし)
一応漢字変換に気をつけ、原稿用紙風に1行20字にして、名前だけは
5年生だと漢字で書かされたような記憶があるので漢字表記にしてみたり、
親の呼び方も、「父」「母」にしなさい。って言われる年のような…
とかいった感じなんですが、実際はどうなんでしょうね?
一番上の弟・平太との年の差(6歳)からすると、実のお父さんのことも
お母さんが再婚した時のこともよく覚えていない気がしたので、以前は
素直にお父さんに懐いていたのではないか。…といった発想から。
ほのぼのを期待していた方はごめんなさい。
しかも「用具父子」なのに、すれ違いだしおチビ出て来てないし伊作出張ったし…
2008.11.24
3/15ほんの一部だけ違うバージョン書いたてあったのを発掘したので、よろしければどうぞ
戻